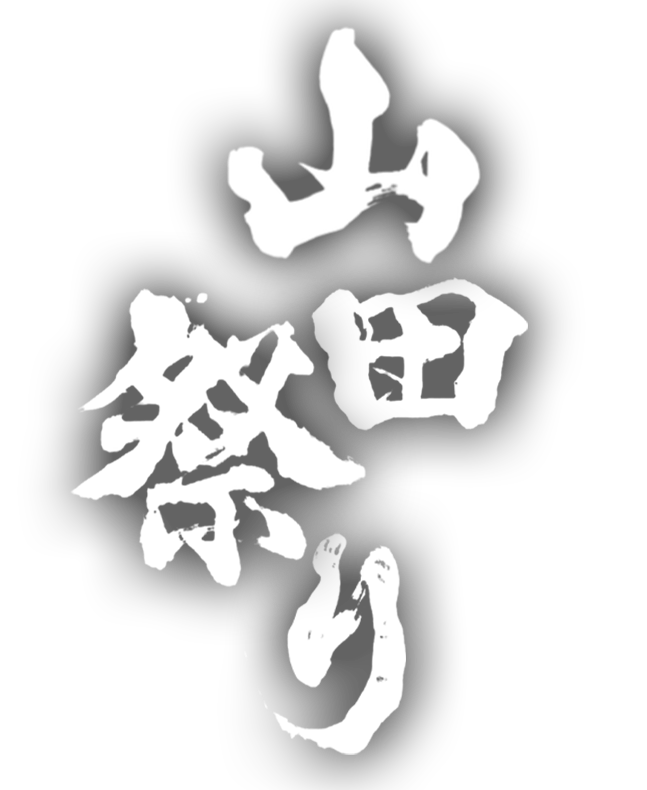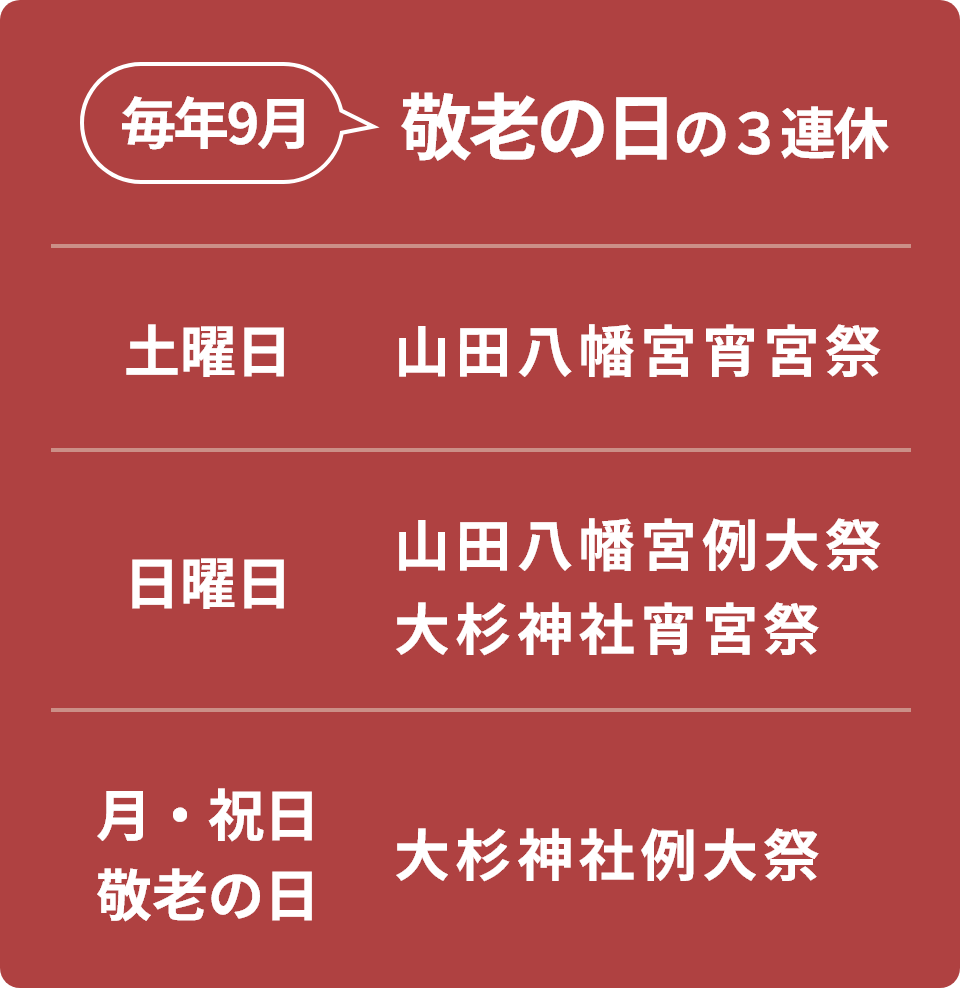MOVIE
動画ギャラリー

岩手 三陸
山田祭り
― 海神と生きる町 ―
“盆正月は帰らず、祭りに帰る”
平凡な日常が流れゆくこの町も
祭りの日には老若男女
ここぞとばかりに人で溢れかえる。
1年が、祭りに始まり、祭りに終わるこの町は
全国的にも有数の “お祭り愛” と
“熱気” に満ちた漁師町だ。
山田祭りとは?
「山田八幡宮」「大杉神社」
2つの神社の例大祭の総称

山田祭りは、「山田八幡宮」と「大杉神社」
2つの神社の“宵宮祭”と“例大祭”を合わせた
3日間の祭りの総称として親しまれています。
その中でも、神霊を神輿に移し町内を巡行する
神幸祭「山田の神幸行事」は
令和6年に岩手県の無形民俗文化財に指定され
独自の文化が続く伝統ある祭りとして今なお
地元の人々に受け継がれています。
山田の「暴れ神輿」
― 神霊の宿る神輿と気迫に満ちた舎人 ―

山田祭りのメインは「暴れ神輿」
早朝に神社を出発してから
夜に境内へ帰ってくるまで
“駆けたり” “回ったり” “突っ込んだり”
気迫に満ちた舎人たちが
「わっせ、わっせ」と
朝から晩まで町の中を一日中駆け回ります。
8つの「郷土芸能」
― それぞれの役割を果たし 神輿を囃し立てる ―




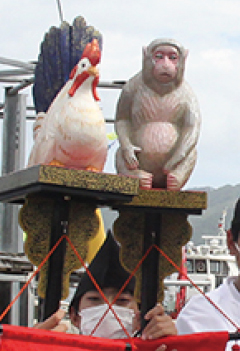



神幸祭では、神輿を8つの郷土芸能が囲み
暴れ神輿を囃し立てながら
町の中を巡行していきます。
神輿の通り道を祓い清める
「八幡大神楽」「山田大神楽」
神輿の後ろで護衛する
「八幡鹿舞」「関口剣舞」
盛り上げ囃し立てる
「境田虎舞」「愛宕青年会八木節」
祭りに彩りを添える「川向十二支」
神様と町民を繋ぐ「関口不動尊神楽」
各郷土芸能団体がそれぞれの役割を果たし
2つの神社の神幸祭を支えます。
山田八幡宮 神輿還御
み はし のぼ
「 御階登り」


山田八幡宮の神幸祭における最大の見どころ。
一日中町を駆けずり周った後
体力の限界を迎えた舎人たちに
待ち構えているのが、最後の難所「御階登り」
この急な階段の先には御宮があり
渾身の力を振り絞って
神輿を階段上の御宮へと納めます。
神輿の重さに耐えきれず、時折崩れる場面も。
神輿を囲む郷土芸能は囃し続け
神輿に集まる観客は声援を送り続けながら
会場が一体となって
神輿が納まるのを見守ります。
この日一番の感動と熱狂に包まれた時間を
ぜひ一度、ご体感ください。
大杉神社 海上渡御
お しお ご り
「 御潮垢離」


大杉神社神幸祭における一大行事。
大杉神社の神輿を船に乗せ
山田湾の入り口に鎮座する“明神崎”
まで赴き、海の安全祈願をする「海上渡御」
早朝に神社を出発した神輿は
海上渡御の前に、浜辺から海に入り
穢れを祓い清める「御潮垢離」を行います。
神輿の海上渡御は各地で見られ
岸壁から船に直接乗せるのが一般的ですが
大杉神社の海上渡御は
神輿を浜辺から小船へ、さらに
綱を手繰り寄せ小舟から輿船(こしぶね)へと
昔から変わらない
伝統的な手法で執り行われます。
この伝統文化が、県の無形民俗文化財として
非常に高く評価され
今もなお変わることなく受け継がれています。
朝一の血気盛んな暴れ神輿が
周りを囲む郷土芸能の
山車に突っ込んでいく“掛け合い”も大迫力です。
ぜひ、早朝の海へ足を運んで
みてはいかがでしょうか。
RULES & TIPS
山田祭りの心得
― 地域のお祭りを楽しむために ―
山田祭りを快適に楽しむために
- 動きやすい服装と履き慣れた靴で参加を
- タオルと水分補給は必須(熱中症対策)
- 突然の雨にはカッパがおすすめ(傘は壊れる可能性あり)
山田祭りは、神様(神輿)を大事にするお祭りです。
神輿を最優先に、以下のことにお気をつけください。
- お神輿を触らない。
→お祓いを受けた舎人しか触ることができません。 - お神輿を建物の2階から見下ろさない。
→神様を見下す行為が失礼とされています。 - お神輿が近づいてきたら道をあける。
→神輿は急に止まることができないので、危険です。
PHOTO
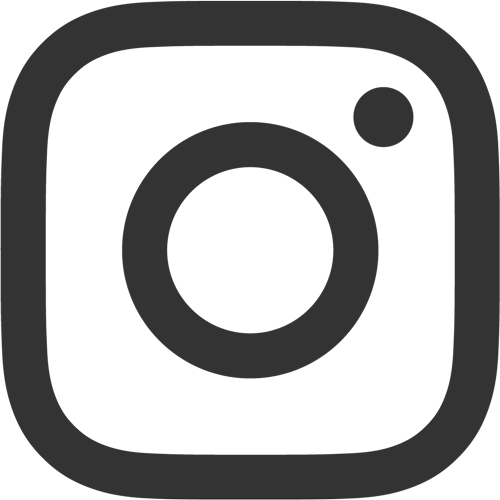
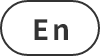

















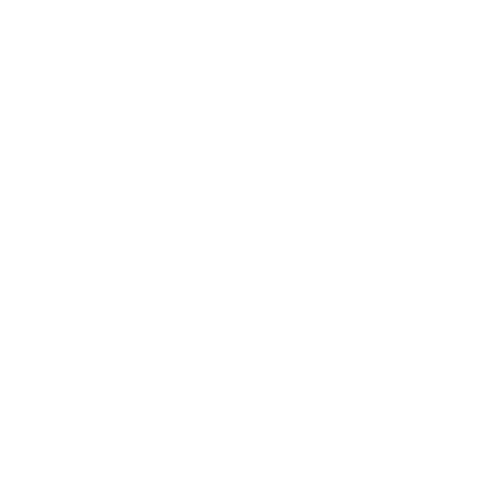 En
En